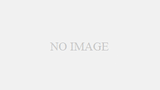七帝柔道に限らず、エビ、逆エビといった寝技の補強運動は一般の柔道にも普及している。這いつくばって進む動作はどう呼ばれているのだろう。私たちは「カメ」と呼んでいたと思うが、七帝柔道記2(p.76) によれば、北大では「這う」と呼ばれていたらしい。また、「寝引き」と呼ぶことが多いとも書かれているが、それは知らなかった。ここでは「カメ」と呼ぶ。一連の補強運動は寝技に必要な筋力のアップと解され、七帝柔道記2でも「筋力を養う」と書かれている。これが通説だろうが、本当にこんな運動で補強になるのか疑問に思う方もいるのではないか。私も抑え込みに役立つ筋力が得られるとは思えない。それでは意味のない運動かというとそうではない。むしろ重要視していて、今でも道場の隅で実践している。カメは崩れ上をイメージしている。脇を締める意識は必要であるが、力を入れるより脱力すべき状況ではないか。だから、試合で「がっちり、がっちり」と声援があると違和感を覚える。なぜカメを重要視しているかというと、崩れ上の意識付け、いわばフォーム作りである。筋トレとは考えていない。相手に乗らないように下がって腹を落とす抑え込みをイメージしたい。小坂師範のオリジナルだと思うが、端まで到達した時、最後に下がる動作を追加している。これはテッポウ対策をイメージしていて、特に注力している。下がるだけでなく、出来るだけ脱力を意識している。カメは脇を締める度に前に進む。別に前に進みたいわけではなく、勝手に進んでしまうのだ。下がる動作を意識したいので、進む度に下がるようにすると、ずっと同じ場所に留まる。現役の様子を見ていると、しばしば背中が丸まっていて、崩れ上に当てはめるとしがみついているように見えてしまう。価値観の差に過ぎないかもしれないが、これまでの認識と違っていたら検討してみてはどうだろうか。
寝技の補強運動
 柔道
柔道