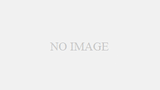七帝柔道記IIの最後に心臓病で最後の大会を断念することになった選手の話が出てくる。直前まで隠して練習していただけに無念だっただろうと思う。実は私も同じ事態になりかねなかった。学生時代には見つかっていなかったが、後に先天的な弁膜症が見つかる。しかも主治医によって判断は大きく異なる。制限の厳しい医師なら練習禁止である。経緯は「名大柔道」にも寄稿したが、後日に診察を受けたので現状まで記載する。
小学生の頃に心臓がチクチクする気がして親に話したが、「成長期にはあるものだ。心臓に異常などあるはずがない。」と一蹴され、心臓病は見逃される。もし重大な疾患であれば、親は一生後悔することになったであろう。30代になっても症状は変わらず気になって循環器内科を受診する。24時間のホルターを着けるなどの検査をした。不整脈は見られるが異常なしとまたも見逃される。展開があったのは40代前半に一過性黒内障という症状が出た時である。視野の半分が一時的に突然欠損するという症状である。30秒から1分ほどで回復したが、当然恐怖を感じる。国立病院の眼科に行った。これは眼の問題ではなく全身的な問題であると言われた。原因や病名について説明もされず、そのまま帰されてしまった。1年くらい経って再び発症した。今度は循環器内科を受診した病院に行った。一過性黒内障と診断され、原因の説明があった。目の血管は心臓から頸動脈を経由して眼球の上下に分かれている。下半分の視野が欠損したということは、上部の血管に血栓が詰まって血液が届かなくなったということである。すぐに流れたため無事回復したが、1時間ほど回復しないと永久に回復しなくなるという。血管の問題ということで循環器内科に回された。
前回と同じ医師だった。今回は心エコーも計測され、逆流が見つかった。造影剤を入れて映像を撮るために検査入院となった。カテーテルを手首から心臓まで通して造影剤を流す。この検査を受ける患者の多くは病気のため血管がボロボロで、私の場合は健康な血管で非常に楽だったそうだ。一泊したのは動脈からカテーテルを通したので、塞がるのを確認するために一晩必要だったらしい。主治医が来て映像を見せてもらった。素人目には酷い逆流でびっくりした。大動脈弁閉鎖不全と説明された。生活には一切支障がなく、運動も全く制限なしという。前回の診察時にすでに異常があった可能性を聞いても返事はなかった。運動制限はないので、むしろ心肺機能を高めるような練習をするようになった。
指にできた腫瘍を大学病院で切除することになった。弁膜症があるため手術前に循環器内科の診察を受けた。医大生が見学する中、老医師が聴診をした。「ノイズは微かであるが、見逃すほどではない」と学生に語った。事前に知っているから分かるだけではないかとも思った。柔道をしていると話すと、「これは軽いものではない。運動はジョギング程度にしなさい。」と言った。聴診だけでそこまで分かるのかと不審に思った。この内科医が現役時に診察していればドクターストップがかかったはずだ。2人の医師の見解は正反対に分かれた。どちらが正しいのだろうか。
主治医が退職するということで、血管外科に回された。そこで初めて弁膜症が先天的だと知らされた。大動脈弁は3つあるが、2つがくっついた二尖弁として生まれた。一番多いタイプの心臓の奇形だという。心臓の大きさなど数値を元に評価を下していて、これまでの医師の中で一番説得力がある。手術に至る事例は珍しくなく、他の部屋に影響が及ぶようになる時が手術の目安で弁移植となる。運動は推奨されるが、選手を目指すような運動はできない。練習量の目安は示されないので、とりあえず乱取りは連続しない方針にした。
仕事を辞めて名古屋に帰った。後輩に勧めてもらったハートセンターを受診した。初回は紹介状と前の病院でのデータに基づいての診察で心電図だけ計測した。主治医は院長だった。「このまま逃げ切れるんじゃないか」と言う。運動の可否は「全く問題なし。もっと酷い状態でハンドボールの日本代表になっている奴もいる。」と言うので、心臓の問題は重要ではなくなった。そもそも上位者との練習は2本続けると相手にならなくなるので続けられないことには変わりない。格下との練習ならヘロヘロになっても続けられそうだ。2回目の診察でCTとエコー。主治医も「まあまあ漏れとる」との感想なので、乱取りが長持ちしないのも仕方なしかな。考えてみれば脂肪を大量に乗せた上で活躍している選手も多いので、ハンディキャップとしては大した問題ではないのかもしれない。