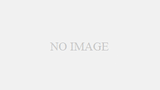高専柔道のある試合について検索していたところ、残念ながら目的としていた情報は得られなかったが、高専柔道に関する学術論文があることを知った。今回見つかった文献について記録しておこう。まず、次の3編が見つかった。
- 高専柔道大会の成立過程:競争意識の台頭と試合審判規定の形成過程に着目して(体育学研究)
- 四帝大大会成立過程における「柔道のスポーツ化」論の出現とその歴史的意味:1918-1928年における学生柔道と講道館の関係に着目して(体育学研究)
- 旧制二高柔道部の歴史的実態:1893-1914念を中心に(スポーツ科学研究)
著者は中嶋哲也先生で現在は茨城大学の准教授らしい。論文は早稲田や鹿児島大学に在籍だった時に書かれたようだ。学部は埼玉大学、大学院は早稲田大学出身ということで、高専柔道には馴染みが無かったと思われるが、研究テーマにしたいきさつには興味がある。参考文献リストを見ると、よくこれだけの文献を見つけてきたものだと感心する。
参考文献から大久保英哲先生の「旧制高等学校のスポーツ活動研究 -練習日誌『南下軍』からみた四高柔道部の修道院化-」が見つかった。スポーツ科学研究という出版物に掲載されているようだが、特別寄稿となっているので査読のない論文かもしれない。彼も福島大学卒で、どのように高専柔道に行きついたのだろうか。附記に記載されていることに驚いた。
また本研究に際し、三浦一哉(2003)、四高柔道部日誌『南下軍』の研究、金沢大学教育学部平成14年度卒業論文を参考にしている。
2000年代になって、まさか高専柔道を卒論テーマにする学生がいたとは思わなかった。資料とされた柔道部日誌は金沢大学には残っているのか。これまで目にすることのなかった文献が取り込まれているのは、私にとっても新しい情報が得られて有難いことである。
更に、京大OBの岡本先生が富山県立大学紀要に「高専柔道の特長と意義について」を寄稿しているのも見つかった。これは七帝出身者にとっては情報源がほぼ同じなので、既知の事実を簡潔にまとめてくれた内容となっている。ここまでが今回オンラインで手に入った文献である。手に入らなかったが、三船朋子さんの東北大学に提出した修士論文
旧制高等学校下位文化としての「高専柔道」の特徴 -明治・大正期における学生柔道から-
には興味がある。彼女が東北大学の柔道部と関係があったかどうかは知らない。
(2024/6/23 追記) さらに検索して、大久保英哲先生の文献2編が見つかった。いずれも金沢大学教育学部紀要に収録されている。
- 旧制第四高等学校のスポーツ活動研究(1)一大正3年柔道部「練習日誌」から-
- 旧制第四高等学校のスポーツ活動研究(2)-昭和2~3年(井上靖在籍当時)の柔道部練習日誌から-
(2024/7/13 追記) 東北大学大学院に修士論文を提出した三船さんは仙台二高の教員で、柔道部顧問も務めておられます。2024年の部誌に寄稿されたそうで、東北大学柔道部と交流はありそうですね。東北大学OBの大森さんが調べてくださり、情報をご提供いただきました。ありがとうございました。
(2024/8/4 追記) 三船さんの修士論文が東北大学OBの大森さん経由で入手できました。一般公開はできませんが、七帝柔道関係者には再配布可能とのことです。